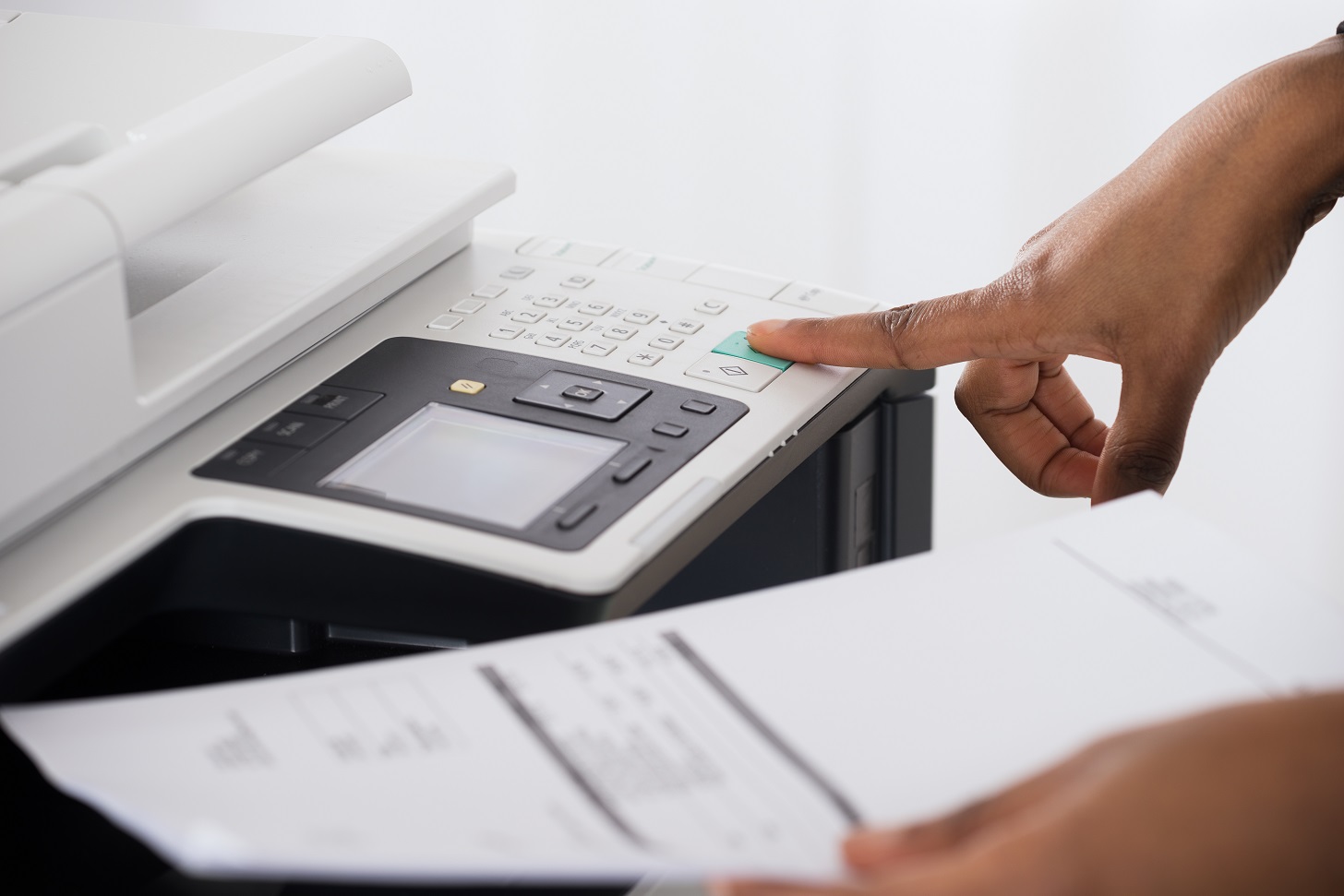食品卸業界では、現在もFAXや電話で受発注業務を行っている企業も多くあり、DX化が業界全体の課題となっています。業務効率化を実現して生産性を高めていくためには、受発注業務もBtoB-ECに置き換えてデジタル化する必要があります。
食品卸のBtoB-ECを新たに構築する場合、以下の4つの方法があります。
◆食品卸のBtoB-ECの4つの構築方法
② カスタマイズが可能なSaaSを利用する
③ パッケージを使用して構築する
④ フルスクラッチ開発で構築する
この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、食品卸のBtoB-ECシステムの4つの構築方法を解説します。
食品卸のBtoB-ECシステムの4つの構築方法
食品卸のBtoB-ECシステムでは、特有の取引条件や多品種管理に対応する必要があります。4つの導入方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、自社の事業規模や要件に合わせて、最適な構築方法を選定しましょう。
◆食品卸のBtoB-ECシステムの4つの構築方法
| ① ASP | ② カスタマイズが可能なSaaS | ③ パッケージ | ④ フルスクラッチ | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 数十万円程度 | 数千万円~ | 数千万円~ | 数千万円~数億円 |
| 個別要件への対応 | △ 食品卸業界向けの主要なEC機能には対応可能 |
○ カスタマイズにより対応可能 |
○ カスタマイズにより対応可能 |
◎ 自社の要件を完全に反映した機能を開発/実装できる |
| カスタマイズ性 | × 低い、軽微な設定変更のみ可能 |
○ 高い |
○ 高い |
◎ 極めて高い |
| 導入スピード | 数日~数か月程度 | 半年以上 | 半年以上 | 1年以上 |
| 外部システム連携 | △ API連携で制限付きで可能 |
○ 可能 |
○ 可能 |
○ 可能 |
| システムの陳腐化 | ◎ クラウドサービスなので常に最新の状態を維持 |
◎ クラウドサービスなので常に最新の状態を維持 |
× 自社で最新化対応が必要 |
× 自社で最新化対応が必要 |
出典:筆者が独自に作成
事業規模、予算、解決したい課題(システム要件)により、最適なシステムの導入方法は異なります。
商品点数や複雑な取引条件が少なく事業規模が比較的小規模の場合や、初期コストを最小限に抑えてスモールスタートで始めたい場合は、方法①のASPを利用する方法が適しています。ASPサービスは年々進化しているため、小規模の場合には標準機能だけでもBtoB-ECを始めるためには十分に役立ちます。
中規模から大規模で、業務が複雑だったり商品点数が多かったりする場合や他システムとの複雑な連携が必要な場合には、方法②のカスタマイズが可能なSaaSの利用や、方法③のパッケージを使用した構築のいずれかの方法が良いでしょう。
特に方法②のSaaSの利用であれば、システムの陳腐化の問題を考慮しなくて済むため、システムの保守・運用コストと定期的に発生するリプレース費用が不要になります。
方法④のフルスクラッチ開発で構築する方法は、完全に独自のシステムを構築することができますが、その分、莫大な初期費用と開発期間が必要になり、さらにシステムの陳腐化の問題にも自社で対応していく必要があります。
食品卸のBtoB-ECに求められる9つの代表的な機能
食品卸業界のBtoB-ECに求められる代表的な機能は以下の9つです。
◆食品卸のBtoB-ECシステムに求められる9つの主要機能
② スマホ発注
③ 商品管理
④ 取引先管理
⑤ 在庫管理
⑥ 分析
⑦ 見積書作成
⑧ OCR/代理注文
⑨ アカウント管理
それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。
機能① 受発注管理
BtoB-ECシステムで受発注業務を行うための機能です。データはすべてデジタル管理され受発注手続きが可視化されるため、人的ミスの削減と業務効率の大幅な向上につながります。
食品卸業界では特定の時間に注文が集中する傾向があり、受発注担当者の業務負荷が一時的に高くなりがちなのですが、EC化することで注文を24時間365日受け付けることも可能になり、業務負荷を分散できる可能性があります。
食品卸業界に限らず、人手不足が常態化している日本では、受発注業務のデジタル化も避けることのできない取り組みの一つと言えるでしょう。
機能② スマホ発注
PCだけでなく、モビリティの高いスマートフォンやタブレットなどからも注文ができる機能です。
食品卸業界の取引先担当者は店舗で注文をするケースもあるため、「前回と同じ内容をワンクリックで再注文できる」といったシンプルかつ便利なUIを実装することが大切です。注文時の操作性は、年間売上の増減にも影響する重要な要素です。
機能③ 商品管理
ECで商品情報を管理する機能です。商品番号を付与することで、商品の基本情報と注文情報をひも付けて管理することもできます。
アナログで商品管理をしていると、ファイルの整理に手が回らず、体系的に管理できていないという企業も少なくありません。BtoB-ECを導入すると、商品情報も適切に管理・活用できるようになります。
機能④ 取引先管理
BtoBの場合には、取引先企業ごとに例えば以下のような値が異なります。
◆取引先企業ごとに異なる値
・卸売価格(掛け率)
・決済方法
BtoB-ECでは取引先ごとに表示する商品や価格、決済方法等を設定することができ、取引先担当者が自分のアカウントでログインすると、画面にはその取引先の情報だけが表示されます。
他の顧客(アカウント)の情報を参照することはないため、安全に取引を行うことができます。
機能⑤ 在庫管理
アナログの受発注管理では、受注担当と出荷担当が異なる場合には正確な在庫数をすぐに把握することは困難ですが、在庫情報もBtoB-ECで管理することで、リアルタイムで在庫状況を常に確認できます。
BtoB-ECサイトにログインすれば、いつでもリアルタイムの在庫状況を確認できるため、在庫切れによる受注トラブルの発生を抑制できます。その結果として、顧客満足度の改善や機会損失の回避が期待できます。また、在庫回転率の把握や余剰在庫の早期発見にも役立つため、データ駆動の意思決定が可能になります。
機能⑥ 分析
BtoB-ECシステムで収集・管理している正確なデータを使用して分析とレポート作成を行うことができます。例えば、取引先のECサイトのアクセスログを分析し、アクセス数やアクセス時間、人気商品や閲覧傾向などを知ることも可能になります。
分析機能を活用して需要予測や購買傾向分析を行い、販売戦略や在庫管理に活用することで、より精度の高い在庫管理や効果的な営業活動を行えるようになります。
機能⑦ 見積書作成
取引先の発注担当者がBtoB-ECサイトにログインし、過去の見積書を流用したり新規の注文を入力したりして見積書を作成し、ダウンロードして稟議申請等の添付資料として使用することができます。
機能⑧ OCR/代理注文
BtoB-ECを導入しても、取引先によっては従来のメールやFAX/電話での注文を希望される場合もあります。そうした場合でもOCR機能では、スマートフォンのカメラで注文書を読み取ることで、BtoB-ECの注文データとして自動登録することができます。
また電話注文などの場合には、代理注文機能で、取引先に代わって注文情報を入力することが可能です。
原則としては、すべての取引先にBtoB-ECサイトを利用してもらうべきですが、取引先企業ごとに事情や業務フローも異なるため、これらの補助機能を実装して、緩やかにデジタル化を推進していけるようにしましょう。
機能⑨ アカウント管理
取引先ごとのアカウント情報と権限を設定・管理する機能です。
アカウントごとに取引額の上限等も設定できるため、例えば新規取引先には上限を低めに設定し、取引実績が増えたら上限を引き上げるなどの柔軟な運用が可能です。
また、取引先企業に複数の担当者がいる場合には、担当者ごとに発注権限・承認権限・閲覧権限などの権限を設定することもできます。
基幹システムとBtoB-ECシステムの役割分担
BtoB-ECを導入することで受発注業務を効率化することができますが、基幹システム(在庫管理、販売管理、会計管理などの企業の中核システム)と連携させなければ、部分的に手作業のプロセスが残ってしまいます。
しかし、完全なシステム連携を行おうとすると、莫大なコストがかかるうえ運用も複雑になるため、基幹システムとBtoB-ECシステムの役割を明確に定義し、「どの範囲までを連携させるべきか?」を十分に検討することが大切です。
役割分担を定義する際には、例えば、ASPを利用してBtoB-ECを開設・テスト試行し、課題を徹底的に抽出してみる、なども効果的です。
BtoB-ECシステムの導入は、大企業であれば莫大なコストがかかり、完全な移行までに数年かかるプロジェクトとなるケースが一般的なので、安全を期して、検討時にテスト試行し、その結果に基づいて本導入を行う方法を取る企業もあります。
中・大規模食品卸企業のシステムに求められる要件
食品卸業界では取引先企業ごとに業務フローや商習慣が異なるため、BtoB-ECシステムの運用も複雑になります。そのため、特に中・大規模の食品卸企業では、複雑なシステム要件が多く、以下に対応したシステムが求められます。
◆中・大規模食品卸企業で求められるシステム要件
・システム連携ができる
・現行の業務フローをそのままデジタル化できる
こうした要件には、冒頭で解説した「食品卸のBtoB-ECシステムの4つの構築方法」のうち、方法①のASPを利用する方法では対応できないため、カスタマイズやシステム連携が可能な方法②③④のいずれかの方法でシステムを構築する必要があります。
◆複雑な業務に対応できるシステム構築方法
方法③ パッケージを使用して構築する
方法④ フルスクラッチ開発で構築する方法
方法④は、自由度は高いもののゼロから開発を行うため最もコストが膨らむため、最初からBtoB-ECの基本機能を備えている方法②のSaaSや方法③のパッケージにカスタマイズを加える構築方法を選択するほうが費用対効果は高いでしょう。
また、方法③のパッケージと方法④のフルスクラッチ開発は、OSとハードウェアやネットワークインフラ、セキュリティ環境も自前で構築する必要があるため、システムの陳腐化の問題やセキュリティ対応などの保守運用コストも自社で行わなければなりません。
方法②のカスタマイズが可能なSaaSを利用する方法は、複雑なシステム要件にも柔軟に対応でき、クラウドサービスなので常に最新環境のシステムを利用できるため、長期的に見ると、投資回収効率と運用の持続性が高い方法と言えるでしょう。
インターファクトリーの「EBISUMART(エビスマート) BtoB」は、BtoB専用ECプラットフォームです。ご興味のある方は、以下の公式サイトで資料請求をしてみてください。
まとめ
従来のメールやFAX/電話での受注をオンライン化するのは面倒に感じるかもしれませんが、デジタル化によってもたらされる、業務の透明化と効率化、データの正確な管理やデータ活用などは、今や企業の成長を加速するための不可欠な要素となっています。まずは、BtoB-ECシステムを導入して、受発注業務の効率化からDXを始めてみませんか?
食品卸のBtoB-ECシステムの構築を検討されている方は、インターファクトリーのカスタマイズが可能なSaaSサービス「EBISUMART(エビスマート) BtoB」をおすすめします。
サービスの詳細は下記の公式サイトをご覧ください。資料請求も可能です。