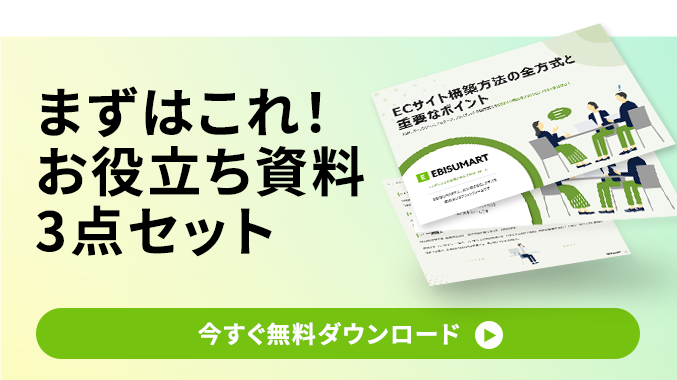ソーシャルギフトは、企業のマーケティング戦略として注目を集めている、新しいギフトの形態です。企業のマーケティング担当者や新しいビジネスモデルを模索している方にとって、従来のギフトとは異なるユニークな特徴を持つソーシャルギフトは、見逃せないトピックです。
この記事では、ソーシャルギフトの基本的な仕組みや特徴を解説し、企業がどのように活用しているのか、具体的な事例を交えてご紹介します。また、今後の市場トレンドや技術の進化についても詳しく探ります。ソーシャルギフトを活用することで、どのようなビジネスチャンスが広がるのか、一緒に考えてみましょう。
ソーシャルギフトとは?基本的な仕組みと特徴
ソーシャルギフトは、デジタル時代における新しい贈り物の形態として注目されています。従来のギフトとは異なり、オンラインで手軽に贈ることができるため、忙しい現代人にとって非常に便利です。
ここでは、ソーシャルギフトの基本的な仕組みとその特徴を解説します。
ソーシャルギフトの定義
ソーシャルギフトとは、インターネットを通じて贈り物を送ることができるサービスを指します。具体的には、メールやSNSを利用して、受取人にギフトカードや商品受け取りのためのURLを送信することが一般的です。このようなギフトは、物理的なプレゼントを送る手間を省き、受取人が自分の好きなタイミングで利用できるという利点があります。
ソーシャルギフトの主な特徴
ソーシャルギフトの主な特徴は、手軽さと柔軟性です。送信者は、オンラインプラットフォームを通じて簡単にギフトを選び、送信することができます。また、受取人は自分の都合に合わせてギフトを受け取ることができるため、受け取る側の満足度も高まります。さらに、ギフトの種類も多様で、食品やファッション、エンターテインメントなど、さまざまな選択肢があります。
ソーシャルギフトと従来ギフトの違い
ソーシャルギフトと従来のギフトの大きな違いは、贈り方と受け取り方にあります。従来のギフトは、物理的な商品を直接手渡しするか、配送する必要がありますが、ソーシャルギフトはデジタル形式で送信されます。これにより、距離や時間の制約を受けずに贈り物を送ることが可能です。また、受取人は自分の好きなタイミングでギフトを利用できるため、よりパーソナライズされた体験を提供します。
ソーシャルギフトの市場動向と利用が増えている背景
近年、ソーシャルギフトは個人間の贈り物としてだけでなく、企業のマーケティング戦略としても注目されています。企業は新たな顧客層を開拓し、ブランドの認知度を高めることが可能となっています。
さらに、ソーシャルメディアの普及により、ギフトの贈り方が多様化し、手軽に感謝の気持ちを伝える手段として利用されています。
ソーシャルギフトが拡大する要因
まず、スマートフォンの普及により、いつでもどこでもギフトを贈ることができる利便性が大きな要因です。これにより、消費者は時間や場所に縛られずに贈り物を選ぶことが可能になりました。
また、ソーシャルメディアを通じた口コミ効果も見逃せません。友人や家族がソーシャルギフトを利用している様子を目にすることで、他のユーザーも興味を持ち、利用を始めるケースが増えています。これらの要因が、ソーシャルギフトの市場拡大を後押ししています。
ソーシャルギフトを支える最新テクノロジー
ソーシャルギフトの普及を支える技術について、QRコードやバーコードを利用したデジタルギフトカードの普及が挙げられます。これにより、受取人は簡単にギフトを受け取ることができ、贈り手も手軽にギフトを送ることが可能です。
さらに、AI(人工知能)を活用したレコメンド機能も重要です。ユーザーの過去の購入履歴や好みに基づいて、最適なギフトを提案することで、よりパーソナライズされた体験を提供しています。これらの技術が、ソーシャルギフトの利便性と魅力を高めています。
ソーシャルギフト利用ユーザーの特徴
ギフトモール オンラインギフト総研の調査では、10~20代の若年層では少額ギフトが多く贈られている一方、50代では1万円以上の高価格帯のギフトも利用されていることが分かります。

出典(画像):株式会社ギフトモール プレスリリース「〜2025年版ソーシャルギフト利用実態調査〜『気持ち』を贈る新文化。気軽に『気持ち』を贈る10~20代、50代では1万円以上の本格ギフトも贈る人も」(2025年8月27日発表)
若年層は気軽な少額ギフトで感謝の気持ちなどを込めたソーシャルギフトを贈る傾向にあり、年代が上がるにつれて誕生日プレゼントやお中元・お歳暮などの本格的なギフトにも活用されていることが読み取れます。ソーシャルギフトを導入する事業者は、自社の顧客層を分析することでより高い効果を得られるでしょう。
ソーシャルギフトを活用した企業事例3選
ここでは、具体的な企業事例を通じて、どのようにソーシャルギフトがビジネスに活用されているのかを紹介します。
事例① 高島屋オンラインストア
高島屋オンラインストアでは、住所や姓名が分からない相手にもメールやSNSでギフトを贈れる「ソーシャルギフトサービス」を提供しています。
高島屋の約3,000点の商品からギフトを選ぶことができ、贈り主と受取主がお互いの住所を知らなくてもギフトを贈ることが可能です。また、受取主がギフトの受取場所や日時を指定できます。
誕生日などの記念日当日でも、ギフトのURLを送ることでお祝いや感謝の気持ちを伝えることができます。
参考:ECzine「高島屋オンラインストア、ソーシャルギフトサービスを開始」(2023年5月22日)
事例② サントリー
サントリーでは、LINEスタンプとアルコール飲料のドリンクチケットを贈れるソーシャルギフトサービス「ノンデネ」を提供しています。
LINEだけでなく、メール、Instagram、XなどのSNSでもURL形式で送付可能で、贈られた相手は8種類の商品から1つを選び、コンビニで実物を受け取ることができます。1回あたり290円(税込)と手ごろな価格なため、気軽に気持ちを伝えるソーシャルギフトとして活用が期待されます。
参考:MarkeZine「LINEスタンプとお酒で気持ちを届ける サントリーの新ソーシャルギフトサービス、『ノンデネ』開始」(2025年8月19日)
事例③ @cosme
美容系総合ポータルサイト「@cosme」を企画・運営する株式会社アイスタイルは、コスメのeギフトサービス「@cosme eGIFT」を提供しています。
1,000円から10,000円までの4段階の金額から選べるデジタルギフトで、SNSやメールで手軽に送ることができます。ギフトを受け取った人は、@cosme公式通販「@cosme SHOPPING」の約5万点の商品から選んだり、@cosmeのフラッグシップショップやコスメセレクトショップで商品を試したり、美容部員に相談しながら選んだりすることが可能です。
参考:株式会社アイスタイル プレスリリース「@cosme、2025年8月28日(木)に、コスメを選ぶワクワクと楽しさをプレゼントできるコスメのeギフトサービス『@cosme eGIFT』をローンチ『贈る』にもっと自由を、『選ぶ』にもっと楽しさを」(2025年8月28日発表)
ソーシャルギフトをビジネスで活用するメリットと注意点
ここでは、ソーシャルギフトをビジネスに取り入れることで得られるメリットと、導入時に注意すべきポイントを詳しく解説します。
ソーシャルギフトの導入は、企業にとって新たなビジネスチャンスを生む可能性がありますが、同時に適切な運用が求められます。ソーシャルギフトのメリットと注意点を把握し、ビジネスにおける成功を目指しましょう。
ソーシャルギフト導入によるメリット
ソーシャルギフトを導入することで、企業は顧客とのエンゲージメントを強化し、ブランドロイヤリティを向上させることができます。特に、SNSを通じたギフトの贈与は、顧客同士のコミュニケーションを促進し、自然な形でブランドの認知度を高める効果があります。
また、ソーシャルギフトは、顧客の購買データを活用したパーソナライズされたマーケティングを可能にします。これにより、顧客一人一人に合わせたサービス提供が実現し、満足度の向上につながります。さらに、オンラインプラットフォームを活用することで、コスト削減や効率的な運用が期待できます。
ソーシャルギフト活用時の注意点と課題
ソーシャルギフトを活用する際には、プライバシー保護やデータセキュリティに十分な配慮が必要です。顧客の個人情報を扱うため、適切な管理体制を整えることが求められます。また、ギフトの選定や提供方法においても、顧客のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。
さらに、ソーシャルギフトの効果を最大化するためには、継続的な顧客分析とフィードバックの収集が不可欠です。これにより、サービスの改善点を見つけ出し、より良い顧客体験を提供することが可能になります。企業はこれらの課題をクリアすることで、ソーシャルギフトを効果的に活用し、ビジネスの成長を促進することができるでしょう。
今後のソーシャルギフト市場のトレンドと展望
ソーシャルギフト市場は、デジタル化の進展とともに急速に成長しています。特に、パーソナライズされたギフト体験や、AIを活用した新しいサービスの登場が予想されます。
ここでは、今後の市場のトレンドや展望について詳しく解説します。
今後のソーシャルギフト技術の進化予測
技術の進化はソーシャルギフトの未来を大きく変える要因です。AIは、消費者の好みを分析し、最適なギフトを提案する能力を持ちます。
また、ブロックチェーン技術は、ギフトのトランザクションをより安全かつ透明にすることが可能です。これにより、消費者は安心してギフトを送ることができ、企業は信頼性の高いサービスを提供することができます。
今後注目のソーシャルギフトサービス
新しいソーシャルギフトサービスが次々と登場し、消費者の注目を集めています。例えば、リアルタイムでギフトを送ることができるサービスや、特定のイベントに合わせたカスタマイズギフトが人気です。
さらに、サブスクリプション型のギフトサービスも注目されています。これにより、定期的に新しい体験を提供することができ、消費者の満足度を高めることが可能です。企業はこれらのサービスを活用し、顧客との関係を強化することが求められます。
まとめ
ソーシャルギフトは、個人間の贈り物の新しい形として注目されています。企業にとっては、顧客との関係を深めるための有効なツールとなり得ます。特に、デジタル化が進む現代において、ソーシャルギフトは手軽さとパーソナライズ性を兼ね備えた贈り物として、ますますその重要性を増しています。
今後、技術の進化に伴い、より多様なサービスが登場することが予想されます。企業はこのトレンドを活用し、顧客満足度の向上や新たなビジネスチャンスの創出を目指してみてはいかがでしょうか。
ソーシャルギフトを導入したECサイト構築を検討されている場合には、インターファクトリーが提供するECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」がおすすめです。EBISUMARTはカスタマイズしたECサイトの構築や、外部システムとの連携にも柔軟に対応できるクラウドECプラットフォームです。
資料のご請求やサービスの詳細については、以下の公式サイトをご確認のうえお気軽にお問い合わせください。