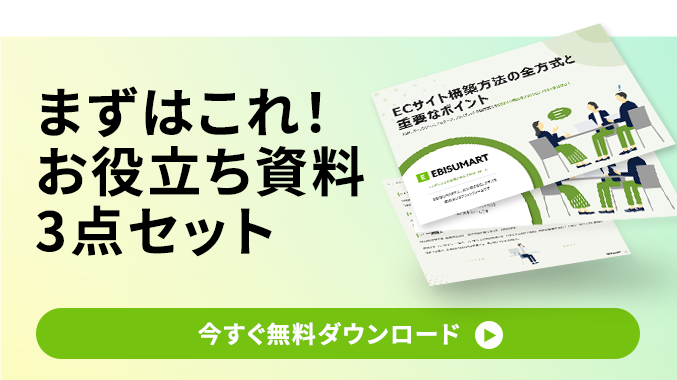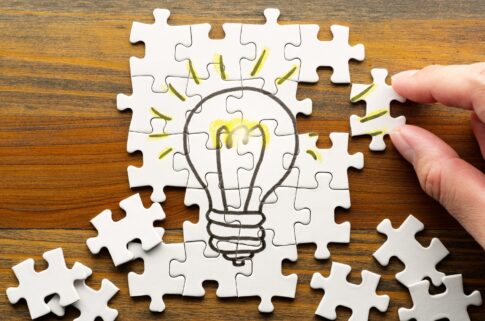「良いレビューが全然つかなくて、売上が伸びない」
「レビュー対策って具体的に何をすればいいの?」
ECサイトを運営していると、“レビュー対策” に頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。
オンラインショッピングが日常化した現在、消費者の購買行動は大きく変化しています。購入前にレビューを確認することが当たり前となり、レビューの少ない商品は選択肢から除外される傾向が強まっているのです。

本記事では、レビューを効率的に集める方法から注意すべきポイントまで、レビュー対策を深掘りして解説します。
◆この記事を読むと得られるメリット
・具体的な施策でレビュー投稿率を大幅に向上できる
・レビュー対策でやってはいけないことが分かる
ECサイトの成功に欠かせないレビュー対策を、体系的に身につけるためにお役立てください。
1. ECサイトにレビューが必要な3つの理由
ECサイトにおいてレビューは、売上を大きく左右する重要な要素です。なぜレビューが不可欠なのか、まずはその理由をしっかり把握しておきましょう。
② 顧客の声が購入の後押しになる
③ レビューが増えるとGoogle検索でも露出しやすくなる
1-1. ほとんどの顧客はレビューを読んでから買う
現代の消費者は商品購入時にレビューを参考にすることが習慣化しており、購入前の情報収集において欠かせない判断材料となっています。
◆顧客がレビューを重視する心理
・情報不足を解消したい:商品説明だけでは分からない使用感や効果を知りたいという心理があります。実際の購入者による生の声は、カタログ情報では伝わらない詳細な情報を提供してくれます。
・失敗を避けたい:オンラインショッピングでは実物を確認できないため、購入後に後悔するリスクを避けたいという強いニーズがあります。他の購入者の体験談は、失敗を防ぐ貴重な情報源です。
・購入を正当化したい:「他の人も満足している商品なら安心」という心理的な後押しを求める傾向があります。多くの高評価レビューがあれば、購入決断への心理的ハードルが下がります。
レビューのない商品は顧客に不安を与え、競合他社の商品に顧客を奪われる可能性が高くなります。
逆に高評価のレビューが充実していれば、コンバージョン率の大幅な向上が期待できます。顧客は安心して購入に踏み切れるからです。
1-2. 顧客の声が購入の後押しになる
レビューは、「商品の魅力を伝える強力な販売促進ツール」としての役割を果たします。
◆レビューが購買行動に与える効果
・具体的な使用場面をイメージできる:「朝の忙しい時間に5分でできた」「子育て中でも簡単に使える」など、レビューでは、商品説明にはない具体的な活用シーンが描かれます。読み手は自分の生活に当てはめて想像しやすくなります。
・サイズや品質のリアルな実態を把握できる:「普段Mサイズだけど、この商品はLサイズがちょうど良かった」「写真より実物のほうが高級感がある」といった実用的な情報が入手できるのは、レビューならではです。オンラインでの購入不安を解消する重要な情報となります。
レビューは、売り手の宣伝文句よりも、はるかに高い信頼性を持っています。第三者による客観的な評価として受け取られるためです。
この信頼性が購入への最後の一押しとなり、売上向上につながります。
1-3. レビューが増えるとGoogle検索でも露出しやすくなる
レビューはSEOにも好影響で、検索エンジン経由の集客力を高める効果が期待できます。
◆レビューがSEOに与える好影響
・関連キーワードが自然に増える:レビューには「コスパ最高」「使いやすい」「おすすめ」など、検索されやすい自然な表現が豊富に含まれます。これらのキーワードが蓄積されていくと、さまざまな検索キーワードでヒットしやすくなります。
・コンテンツが定期的に更新される:新しいレビューが継続的に投稿されることで、ページ内容が定期的に更新され続けます。検索エンジンはフレッシュで活性度の高いページを評価するため、SEO効果が向上します。
・リッチスニペットによる視認性向上が狙える:レビューを適切にマークアップしておくと、検索結果に星評価やレビュー件数が表示されます。この星付きの表示があるだけで、クリック率が向上します。
レビュー数の増加はサイト全体の検索流入数の増加につながり、新規顧客の獲得コストを下げる効果も期待できます。
つまり、レビューは購入率向上と集客力向上の両方を同時に実現する、きわめて効率的な施策なのです。
2. レビューが増えない原因がECシステムに隠れていないかチェックする
レビュー対策に取り組む際は、まず、現在利用しているECプラットフォームがレビュー施策の足かせになっていないか、点検しておきましょう。
というのは、レビュー対策の成果は、ECサイトの基盤システムに大きく左右されるからです。細かな施策に工夫を凝らしても、システム自体がレビュー収集に適していなければ、期待する結果は得られません。
② 良いシステムならレビュー対策は効果が倍増する
③ 成功事例:山善ビズコムにReviCo導入→投稿が11倍に増加
2-1. レビュー対策の成果は土台となるシステムで決まる
機能不足のシステムでは、レビュー施策の効果が半減してしまいます。レビュー投稿の導線が不明瞭だったり、会員登録が必須だったりすると、せっかく協力的な顧客も、途中でレビュー投稿を諦めてしまうからです。
◆レビュー対策がうまくいかないシステムの例
・投稿機能がない・目立たない:レビュー投稿欄が存在しない、または目立たない場所にあるサイトでは、当然ながらレビューは集まりません。商品ページ上の分かりやすい位置に投稿フォームが設置されていることが最低条件です。
・ユーザビリティに問題がある:複雑な会員登録の手続きや入力項目が多すぎる投稿フォームは、投稿意欲を削ぐ大きな要因となります。ワンクリックでレビューページにアクセスできる仕組みが理想的です。
・レビュー依頼の自動機能がない:手動でレビュー依頼を行うのは現実的ではないため、結果として依頼の回数やタイミングが不十分になります。システムの自動化機能がレビュー収集の効率を大きく左右します。
一方、適切な機能を持つ優れたシステムを選択すれば、レビュー集めは格段に効率化され、少ない労力で大きな成果を上げられるようになります。
レビュー対策を本格的に始める前に、まずはシステム環境の整備から取り組むことが成功への近道です。
2-2. 良いシステムならレビュー対策は効果が倍増する
「レビューが集まらない」と悩んだ際は、まず現在のシステムを詳細に検証し、必要に応じて移行(リプレース)も検討しましょう。
これからリプレースを検討される際に重要なことは、クラウドEC型のプラットフォームを選択することです。
クラウドECとは、ASP型の最新性とパッケージ型やオープンソース型のカスタマイズ性を両立できる、今最もおすすめのプラットフォーム形態です。
たとえば、クラウドECプラットフォーム「EBISUMART」では、最新のレビュー機能を搭載していることはもちろん、レビュー対策を強化するツール「ReviCo」と標準連携していることが強みです。
具体的には、以下の効果が期待できます。
・レビュー投稿の促進:簡単にレビュー投稿ができるインターフェースによる投稿ハードルの低下と、ReviCoが実施するレビュー投稿キャンペーンの活用により、レビュー投稿数の増加が期待できます。レビュー数の増加は、ユーザーの購入意欲を高め、CVRの向上に寄与します。
・レビューの分析・活用:レビューを分析、データとして活用することで、事業者様は商品やサービスの改善点が明確になり、顧客満足度の向上と共に、リピーターの増加や新規顧客の獲得につながります。
・ECと実店舗の垣根を超えた活用:実店舗でもQRコードを利用したレビューの収集・表示が可能です。実店舗でのレビュー収集により、ユーザーの生の声を迅速に販売戦略に反映し、サービスの質向上に役立つほか、店舗の集客力向上や顧客満足度の向上が期待できます。
・EC運営の業務効率化:投稿されたレビューに対しての返信を自動生成します。EC運営の業務を効率化することで、事業者様はより戦略的な業務に集中できるようになり、対応品質の向上による顧客満足度の向上やリピーターの増加が期待できます。今後も生成AIを活用した、さらなるレビュー業務の効率化を実現していきます。
出典:株式会社インターファクトリー プレスリリース「クラウドコマースプラットフォーム『EBISUMART』がレビューマーケティングプラットフォーム『ReviCo』との連携を開始。」(2025年8月26日発表)
2-3. 成功事例:山善ビズコムにReviCo導入→投稿が11倍に増加
EBISUMARTとReviCoの標準連携がスタートしたのは2025年8月ですが、これに先立ち、EBISUMARTで運営されているBtoB-ECサイト「山善ビズコム」にて、ReviCoを先行導入しています。

出典:山善ビズコム
導入後、ECサイト上でのレビュー投稿が約11倍に増加し、ユーザーの購買意欲を高めることに成功しています。
EBISUMARTの詳細は、以下の資料にてご確認いただけます。
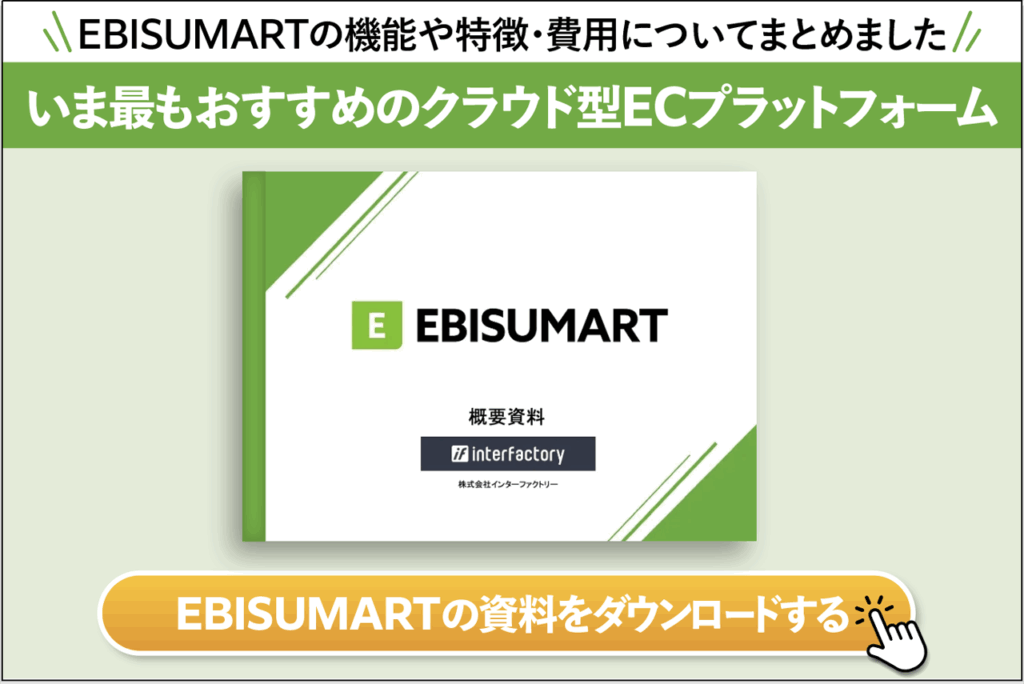
3. 明日からできる!レビュー率が上がる対策 4選
システム環境が整ったら、次は具体的なレビュー収集施策の実践です。ここでは、特別な予算や技術を必要とせず、明日からでも実施可能な施策をご紹介します。
② 次回使えるクーポンでささやかなお礼をする
③ 手書きメッセージで感謝の気持ちを伝える
④ レビューの書き方を分かりやすく案内する
3-1. 商品到着後のベストタイミングでメールを送る
レビュー依頼は、商品特性や顧客の使用状況を考慮した最適な配信時期を見極めることが重要です。
レビュー投稿率は「いつ頼むか」のタイミングに大きく左右されます。早すぎても遅すぎても効果は期待できず、顧客が商品を十分に体験した直後のタイミングを狙う必要があります。
◆効果的なレビュー依頼のタイミング設定
・最適なタイミングを見計らう:食品や消耗品なら到着から3〜5日後、ファッションアイテムなら1週間後、家電製品なら2週間後など、実際の使用感が得られるタイミングを見計らいます。使用開始から顧客の中に感想や評価が生まれるまでの期間を考慮しましょう。
・配送期間を考慮して調整する:注文から到着までの配送日数を加味して、「注文から●日後」ではなく「到着から●日後」を基準に設定します。地域による配送期間の差も考慮すると、より精密になります。
・フォローアップメールの内容を工夫する:件名に「△△はいかがでしたか?(●●様限定特典あり)」など開封を促す文言を入れ、本文では商品への満足度を気遣う温かいトーンで依頼します。単なる依頼ではなく、顧客との継続的な関係構築を意識した文面作りが大切です。
最適なタイミングは業界や商品によって異なるため、実際の配信結果を分析しながら、継続的に調整してください。効果測定を繰り返し、自社商品に最も適したタイミングを見つけましょう。
3-2. 次回使えるクーポンでささやかなお礼をする
レビュー投稿という手間をかけてくれた顧客に対する謝礼は、“レビュー投稿率の向上” と “次回購入の促進” の両方に効果的な施策です。
過度でない範囲でのインセンティブ提供は、顧客の「協力したい」という意欲を高めます。ブランドに対する好感度の向上にもつながります。
◆効果的なインセンティブ設計のポイント
・適切な特典レベルを設定する:「次回使える10%OFFクーポン」「300円の商品券」など、感謝の気持ちを表しつつも過大にならない範囲での設定が重要です。
・事前に告知する:商品ページや購入完了画面で「レビュー投稿でお得な特典プレゼント」と事前に告知します。購入時からレビュー投稿への意識を持ってもらうと、より高い投稿率を実現できます。
参考までに、前出のレビュー投稿が約11倍に増加した「山善ビズコム」では、『レビューを書いて次回使える10%OFFクーポンプレゼントキャンペーン』を実施しています(2025年9月現在)。
3-3. 手書きメッセージで感謝の気持ちを伝える
デジタル化が進んだ現代だからこそ、アナログな手書きメッセージは顧客の心に深く響くツールとして、あらためて注目されています。
商品発送時に同封する直筆のメッセージカードで、レビューについて触れておくと、投稿率が高まります。
◆手書きメッセージのポイント
・心のこもった文面作り:「●●様 この度は数ある商品の中から当店をお選びいただき、心より感謝申し上げます。(中略)よろしければ、レビューでお使い心地をお聞かせください」など、温かみのある文章を心がけます。顧客一人一人を大切にする姿勢が伝わる内容にします。
・運営効率との両立:すべてを手書きにするのが困難な場合は、一言メッセージだけ手書きにする、本文は印刷にするなど、実現可能な範囲でパーソナライズを図ります。大切なのは顧客への感謝の心を伝えることです。
手書きメッセージには手間がかかりますが、その手間こそが顧客に真心が伝える力となります。こうして培われた顧客との絆が、レビュー投稿率の向上にもつながります。
3-4. レビューの書き方を分かりやすく案内する
レビューを書き慣れていない顧客に対しては、具体的な書き方を案内することも大切です。顧客が何を書けば良いか迷わないよう、親切で分かりやすいガイドラインを準備しましょう。
◆ガイドラインの作成例
・具体的な例を挙げておく:「このシャンプーを1週間使用したところ、髪がしっとりツヤツヤになりました!泡立ちも良く、香りも好きな香りで大満足です」のような具体的なレビュー例(過去に投稿されたもの)を示します。
・書くべきポイントを整理する:「使用してみた感想」「商品の良かった点・改善してほしい点」「どんな人におすすめか」など、レビューに盛り込んでほしい要素を箇条書きで示します。何を書こうか考える負担を軽減しつつ、充実したレビューを書いてもらえる効果もあります。
・質問形式で迷わないようにする:「商品の使いやすさはいかがでしたか」「期待していた効果は得られましたか」「次回も購入したいと思いますか」など、答えやすい質問を用意します。質問に答える形式なら自然にレビューが書けるため、投稿率が大幅に向上します。
上記のほか、レビュー投稿までの導線やレビュー特典の使用法(例:クーポン取得・使用の流れ)なども、明記しておきましょう。
4. これは注意!レビュー対策でやってはいけないこと
一方、レビュー対策を進めるうえでは、避けなければならない行為があります。以下のポイントを確認しましょう。
② 豪華すぎるお礼:法律違反になることもある
③ 良いレビューのお願い:逆に悪い評価を招く
4-1. やらせレビュー:一瞬で信頼を失うリスク
自作自演によるやらせレビューは、一度発覚すれば企業の信頼は失われ、回復はきわめて困難となります。法的にも道義的にも、重大な問題があるからです。
2023年10月のステルスマーケティング規制強化により、こうした行為は明確に景品表示法違反として位置付けられました。
誠実なビジネスの基本は、透明性と信頼性にあります。短期的な評価向上を狙った不正行為は、長期的に見て企業価値を大きく毀損する愚策と言わざるを得ません。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
4-2. 豪華すぎるお礼:法律違反になることもある
レビュー投稿への謝礼提供は一般的な施策ですが、その内容や金額によっては景品表示法違反となるリスクがあります。
法律の規制範囲を理解し、適法な範囲でのインセンティブ設計を行うことが重要です。
◆景品表示法による規制内容
・過大な景品類の提供の禁止:商品価格や取引額に対して不相応に高額な特典は「過大な景品類の提供」として禁止されています。一般的に、総付景品の場合は取引価額の20%が上限(1,000円以上の商品の場合)とされています。
・評価を誘導する特典の問題:「★5評価でクーポン進呈」など、特定の評価を条件とした特典提供は、消費者の自主的判断をゆがめる不当な誘引とみなされ、ステルスマーケティング規制にも抵触するおそれがあります。
適法で健全なレビュー施策のためには、特典設定は常識的な範囲に留める必要があります。法務部門(または弁護士などの専門家)との事前相談も検討しましょう。
出典:消費者庁「総付景品について」
4-3. 良いレビューのお願い:逆に悪い評価を招く
高評価を依頼する行為は、顧客の反感を買い、かえって低評価レビューを誘発する逆効果をもたらします。
「レビューは本来、購入者の自由で率直な感想であるべきもの」という認識が、浸透しているためです。
◆高評価依頼がもたらす悪影響
・顧客心理への悪影響:「良いレビューをお願いします」という依頼は、顧客に対して評価の押し付けをしている印象を与えます。反発が起き、意図的な低評価が増えるリスクが高いでしょう。
・ブランドイメージの毀損:高評価を要求する企業は「評価操作をしている」「商品に自信がない」という負のイメージがつきまといます。ブランド価値の低下は避けられません。
レビュー対策はあくまでも中立的な依頼に留め、評価の高低に関わらず、レビュー投稿そのものに対する感謝を示すことが重要です。
5. まとめ
本記事では「レビュー対策」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。
ECサイトにレビューが必要な3つの理由は、以下のとおりです。
② 顧客の声が購入の後押しになる
③ レビューが増えるとGoogle検索でも露出しやすくなる
レビューが増えない原因がECシステムに隠れていないか、まずはチェックしましょう。
② 良いシステムならレビュー集めはもっと楽になる
レビュー率が上がる対策として以下を解説しました。
② 次回使えるクーポンでささやかなお礼をする
③ 手書きメッセージで感謝の気持ちを伝える
④ レビューの書き方を分かりやすく案内する
レビュー依頼でやってはいけないことは以下のとおりです。
② 豪華すぎるお礼:法律違反になることもある
③ 良いレビューのお願い:逆に悪い評価を招く
適切なレビュー対策は、多方面にわたる好循環を生み出します。本記事の内容を参考に、自社ECサイトの現状を見直し、体系的なレビュー対策に取り組んでいきましょう。