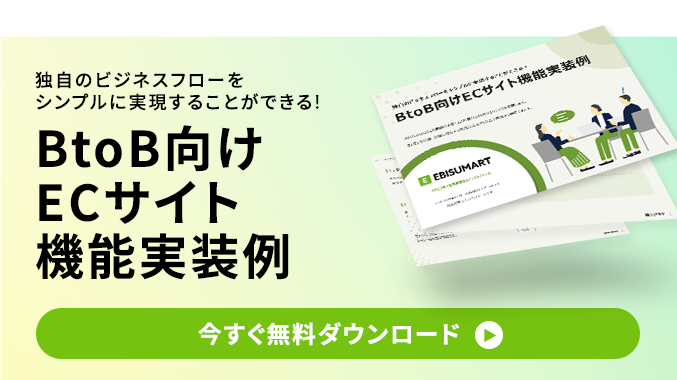営業の商談管理で使用している「SFA(営業支援システム)」とECサイトを連携させることで業務を効率化できます。SFAとECサイトの連携によって、例えば以下のような機能を実現できます。
◆SFAとECサイトの連携で実現できる機能
機能② ECサイトの顧客の行動履歴データをSFAでも利用できる
機能③ ECサイトで見積書を作成できる
機能④ SFAで、ECサイトで自動算出した見積書ごとの利益率/粗利率を分析できる
機能⑤ 顧客がECサイトで発注できる
しかし、例に挙げたすべての機能を一気に実現しようとすると、要件が複雑かつ多岐にわたるため、莫大な費用と労力がかかるだけでなく、失敗に終わる可能性が高いでしょう。また、もし無事にリリースまで漕ぎつけたとしても、現場で活用できなければ無駄な投資となってしまいます。
そのため、SFAとECサイトの連携では、実現したい機能ごとにフェーズを分けて、段階的にリリースしていく方法を取るべきだと筆者は考えています。
この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、SFAとECサイトを連携して業務を効率化する際のポイントを解説します。
SFAとECサイトの連携の失敗例
筆者はかつて、大手外資系企業でシステムエンジニアとして勤務していた時期があり、2008年からのおよそ2年間、サーバを販売する部署のSFAとECサイトの連携システムの導入プロジェクトに参加していました。総額1億円規模のプロジェクトでしたが、結果から言うと、以下の3つの要因により失敗に終わりました。
◆SFAとECサイトの連携システムの導入プロジェクトが失敗した3つの要因
要因② 現場の社員が新しいシステムを積極的に利用しなかった
要因③ 顧客ごとに異なる複雑で多様な見積書作成機能を実現できなかった
歴史のある企業では営業社員ごとに業務フローが属人化しているケースが多く、標準化の取り組みのハードルが高くなります。このプロジェクトでも、営業社員ごと、顧客ごとに見積書の項目もフォーマットも異なっていたことで、見積書作成機能の実現は極めて困難でした。
開発に2年近く費やしたにもかかわらず、リリースから数か月後にはシステム導入以前のアナログでの業務に戻さざるを得なくなり、結局リリースした新システムはお蔵入りとなってしまいました。
この経験から筆者が学んだことは、SFAとECサイトの連携を成功させるためには、最初に複雑な業務フローを整理するとともに、現場でリーダーシップを発揮できるキーパーソンをプロジェクトに引き込むことが重要であるということです。
SFAとECサイトの連携で実現できる5つの機能
それでは、本記事の冒頭で紹介した、SFAとECサイトの連携で実現できる5つの機能について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
◆SFAとECサイトの連携で実現できる機能
機能② ECサイトの顧客の行動履歴データをSFAでも利用できる
機能③ ECサイトで見積書を作成できる
機能④ SFAで、ECサイトで自動算出した見積書ごとの利益率/粗利率を分析できる
機能⑤ 顧客がECサイトで発注ができる
各機能の解説では、筆者の経験に基づいた各機能の「実現難易度」もあわせて掲載しています。
機能① カタログECを導入できる
ECサイトを「カタログEC」としてリリースします。これにより、従来の営業活動や展示会などのイベント、広告などのプロモーション活動のレスポンスだけでなく、ECサイトを介したアプローチが可能になります。
コーポレートサイトに商品ページを掲載している企業は多いですが、自社の商品やサービスを体系的にまとめられているカタログECを導入することで、商品やサービスの情報をより手軽に発信することが可能になります。
カタログECの導入ではSFAとの連携は不要で、ECサイト構築の中で実装できるため、例えば月額数万円程度のBtoB向けECカートサービスでも実現できます。しかし、低料金サービスでは複雑なシステム間連携には対応できない場合が多いため、他の機能を追加していく計画があるのであれば、カスタマイズやシステム間連携に柔軟に対応できるクラウド型ECプラットフォームサービスやパッケージでの構築をおすすめします。
機能② ECサイトの顧客の行動履歴データをSFAでも利用できる
この機能を実現するためには、ECサイトを開設した後、ECサイトの顧客の行動履歴データをSFAで利用できるようにするための仕組みが必要になります。データ連携を実装すると、例えば、顧客がECサイトで商品やサービスの資料をダウンロードしたり、特定ページを閲覧したりした履歴情報を、営業社員がSFA上で利用できるため、データ駆動型の営業活動が可能になります。
データ連携の実装方法はいくつかありますが、比較的容易に実現できるのが「API連携」で、SFAとECサイトの双方にAPI連携機能があることが前提となります。もし、片方あるいは双方のシステムにAPI連携機能がない場合は、新たにAPI連携機能を開発してシステムに組み込むか、ファイル連携やデータベース連携などの別の方法で実現しなければなりません。
各システムのAPI連携機能を使用して実装する場合、APIの仕様と要件が一致していれば、難易度はさほど高くならないケースが多いです。
機能③ ECサイトで見積書を作成できる
商品と購入数量といったシンプルな項目の見積書であれば、ECサイトでも比較的容易に実装できるのですが、BtoB企業、特に多くの顧客を抱えていたり、多様な商品やサービスを提供したりしている企業の場合は、顧客ごとや案件ごとにまったく異なる項目とフォーマットの見積書を自動出力できる仕組みが求められます。
また、BtoBでは顧客ごとに異なる割引率や、作成した見積書の社内承認をはじめとする複雑な運用フローなども存在しており、すべての業務フローを完全にシステム化するとなると莫大な費用と労力が必要になります。
機能④ SFAで、ECサイトで作成した見積書をもとに利益率/粗利率を算出できる
この機能を実現するためには、ECサイトで作成した見積書データから見積書ごとに利益率/粗利率を自動算出するための仕組みが必要になります。
実現難易度は非常に高いのですが、もしECサイトで見積書を作成する機能(機能③)を実装できたら、商品情報に利益率/粗利率を設定することで見積書ごとの収益データを自動算出が可能になります。これらのデータをSFAでも使えるようにすることで、案件ごとの収益性なども分析できるようになります。
機能⑤ 顧客がECサイトで発注できる
この機能を実現するためには、ECサイトにログインした顧客が、発行済みの見積書を指定して発注手続きを行うための仕組みが必要になり、「注文機能」に加え、顧客側企業のワークフローの実装が求められます。
BtoBのソリューションサービス領域では数百万~数千万円規模の商材もあるので、顧客の購買担当が自分だけの裁量で発注手続きを完了できるというケースはまずありません。そのため、発注時にECサイトで承認プロセスを進められるよう、ECサイトに承認フローを実装する必要があります。
現時点ではSFAとECの両機能を持つ市販サービスは存在しないため、必要な場合は新たに構築するしかない
筆者の知る限りでは、SFAとECサイトの両方の機能を標準で搭載しているソフトウェアは現時点では存在していないため、次のいずれかの方法で自社のシステムを構築する必要があります。
◆SFAとECサイトの機能を持つシステムの構築方法
方法② SFA機能を、ECサイトに組み込む
方法③ SFAとECシステム間のデータ連携機能を実装する
方法①のフルスクラッチ開発はよほどの理由がない限りは推奨しません。
SFAにもECシステムにもそれぞれ専門機能があり、すでに市場には成熟したソフトウェアやサービスが存在しています。フルスクラッチ開発は莫大な費用と労力がかかる上、それらと同等以上の機能を持つシステムを開発することは困難です。
また、方法②はECサイトにSFA機能を組み込む方法もあまりおすすめできません。高額なカスタマイズ費用のわりに、既製のソフトウェアやサービスよりも機能面が劣る可能性が高いからです。
そのため、費用を抑えて最大限の効果が得られる最も現実的な方法としては、方法③「SFAとECシステム間のデータ連携機能を実装する」がおすすめです。
SFAとECサイトの連携はフェーズを分けて段階的に!
SFAとECサイトを連携させる場合には、目的ごとにフェーズを分けて段階的に実装していくべきです。一度にすべての機能をリリースしようとすると、十分な要件定義ができずに必要な業務フローをカバーできなかったり、長い開発期間中に業務フローや優先度が変化しリリース時には機能が陳腐化してしまっていたりするリスクが高くなります。
リスクを最小に抑えるためには、例えば以下のように、フェーズを分けて段階的に開発・実装していくようにしましょう。
◆SFAとECサイトのデータ連携実装におけるフェーズ分け例
フェーズ② SFAとECサイト間のデータ連携機能を実装する
フェーズ③ 見積書作成機能や発注機能をECサイトに実装する
フェーズを分けて段階的に実装してリリースすることで、現場に新しい運用を徐々に馴染ませていくことができ、プロジェクト失敗のリスクを減らすことができます。「スモールスタート」と「迅速なリリース」はプロジェクトを成功させる鍵と言えるでしょう。
現場部門をプロジェクトに巻き込む
複数のシステムを連携するといった複雑かつ業務への影響が大きいシステム構築プロジェクトをDX推進部門やシステム部門だけで進めてしまうと、現場の意見がシステム要件にきちんと反映されず、使えないシステムとなってしまうリスクがあります。必ず現場のリーダーをプロジェクトメンバーとして招集し、正しく現状を把握していくことが重要です。
また、プロジェクトメンバーの部門リーダーには、プロジェクトへの部員の関与を促し、新しいシステムの導入に対して部門内に前向きな雰囲気を醸成していく行動が求められます。
多様な見積書の自動作成は生成AIの活躍に期待!
現状、難易度の高いBtoBの見積書作成機能ですが、生成AIの活用が期待されており、過去に作成した見積書の情報を生成AIに学習させることで、個人に依存して作成されて複雑な見積書の作成業務も自動化できる可能性があります。
見積書の自動作成機能に生成AIを組み込む場合には、人間が見積書の内容をチェックして不備をフォローするプロセスも考慮したシステム設計が求められます。
まとめ
SFAとECサイトの連携はそれなりの予算と労力が必要になりますが、導入することで属人化している業務を効率化でき、またデータに基づいた営業活動も行えるようになります。
連携プロジェクトは、いくつかのフェーズに分けて段階的に実装・リリースしていくようにしましょう。その最初のフェーズとして「カタログEC」の導入を検討されている方には、インターファクトリーのクラウド型ECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」がおすすめです。EBISUMARTは柔軟なカスタマイズが可能で外部システムとの連携にも強く、複雑なカスタマイズやデータ連携の実績も豊富です。
「EBISUMART」に詳細については、下記の公式サイトをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。