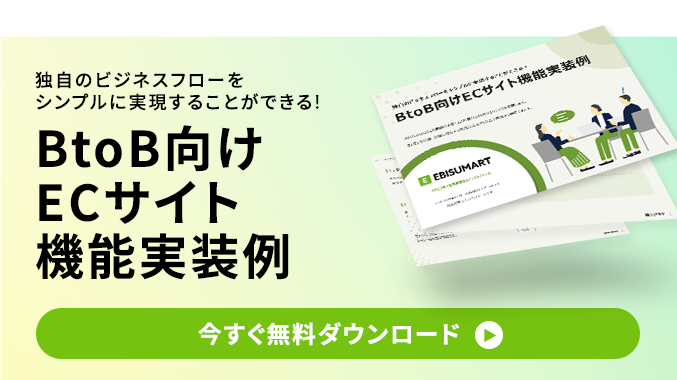経済産業省が2025年8月に発表した「電子商取引に関する市場調査報告書」によると、BtoB市場のEC化率は43.1%にのぼり、前年比で3.1ポイント増となりました。
しかし、日本政府が目指していた「2023年を目途に電子受発注システムの導入率を約5割とする」という方針は、2025年時点でも達成できていません。
出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)
電子受発注システムを導入する方法としては、以下の3つがあります。
◆電子受発注システムを導入するための3つの方法
方法② カスタマイズやシステム連携も可能な「受発注システム」を利用して構築する
方法③ EDIを導入する
中大規模企業の場合には、カスタマイズや外部システムとの連携が必要であることを前提として導入方法を選択する必要があります。
この記事では、株式会社インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、受発注システムをデジタル化する3つの方法と導入するための8ステップについて解説します。
国内BtoB市場のEC化率は43.1%
下図は、国内BtoB市場のEC市場規模とEC化率の2019~2024年の推移を示したグラフです。
◆国内BtoB市場におけるEC化率
.png)
引用(図表):経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)の「図表1-7:BtoB-EC市場規模の推移」
国内のBtoB市場のEC化率は2023年時点で40.0%に到達し、2024年には43.1%まで増えていますが、裏を返すと、約60%の企業は未だにアナログ運用で受発注業務を行っている、ということになります。
FAXや電話、対面等での紙ベースの帳票を使用する従来の運用は、現在もさまざまな業界で根強く残っており、ヒューマンエラーによるミスや処理の遅れなどの非効率を生み出しています。多様な働き方の実現や人手不足の問題に対応していかなければならない企業にとって、デジタル化の遅れは重大な経営リスクとなります。
すでに電子受発注システムを導入している企業では、誤発注の削減、リードタイムの短縮、在庫の最適化などで目に見える成果を生み出し、業務効率と生産性の面で大きなアドバンテージを獲得しています。
今後ますます人手不足とコスト圧力は深刻化するとみられている中で、電子受発注システムの導入は今すぐ取りかかるべき経営課題の一つです。
電子受発注システムの3つの導入方法
電子受発注システムを導入するためには、次の3つの方法があります。
◆電子受発注システムを導入するための3つの方法
方法② カスタマイズやシステム連携も可能な「受発注システム」を利用して構築する
方法③ EDIを導入する
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
方法① BtoB専用のクラウド受発注システムを利用する
クラウド上の専用システムをPCやスマートフォン、タブレットから利用する方法で、最も低予算かつ短期間で導入できます。
BtoB専用電子受発注システムのクラウドサービスは、さまざまな企業から提供されており、一般に以下のような機能が標準機能として実装されています。
◆BtoB専用のクラウド受発注システムの標準機能(例)
・受注情報の登録/閲覧機能
・在庫連携機能/在庫のリアルタイム表示
・受発注のステータス管理機能
・帳票類の自動発行(納品書、請求書など)
・取引履歴の検索/閲覧機能
アナログ運用で使用している紙の情報をテンプレートの項目に沿って入力したり、ExcelやCSVのデータファイルを指定のフォーマットに加工してインポートしたりすることで、現行の情報を電子受発注システムに移行できます。
しかし、機能の追加やカスタマイズ、複雑なシステム連携には対応できないため、利用する場合には業務フローをサービスに合わせる必要があります。そのため、個人~小規模企業に適した方法となります。
方法② カスタマイズやシステム連携も可能な「受発注システム」を利用して構築する
クラウドサービスや専用パッケージをカスタマイズしてシステムを構築する方法です。基本的なBtoB専用の受発注機能は実装されており、個別の機能追加やカスタマイズ、複雑な外部システムとの連携を、追加実装していくことができます。
日本では「業務フローを変えずに、デジタル化したい」と考える傾向が強く、サービスに合わせて業務フローを見直すことを嫌い、システム側を既存の業務に対応させようとする企業は少なくありません。
また、承認のためのワークフローやイレギュラー対応のシステム化、基幹や顧客管理などの他システムとのデータ連携などの実装が必須とされるケースが多いため、開発期間が年単位に及ぶ数億円規模の開発となることも珍しくありません。
方法③ EDIを導入する
EDI(Electronic Data Interchange)は、注文書・納品書・請求書などの取引情報を、紙ではなく電子データで企業間のやり取りをする仕組みで、BtoBの現場では中小企業から大企業まで幅広く導入されています。業界によってはEDIの導入が必須となる場合もあります。
EDIの導入では、専用ソフトや専用回線といった設備投資が必要となることと、取引先や業界ごとにEDI規格が異なることが大きな障壁となっていましたが、近年はインターネットを使用する「Web-EDI」の普及が進み、業界や国単位でEDI規格の共通化を目指す動きもあり、導入しやすい環境が整備され始めています。
例えば、経済産業省の支援で開発された「中小企業共通EDI」の実証事業では、受発注企業ともに約50%程度の業務時間削減効果が確認されています。
出典:中小企業庁「中小企業共通EDI」
EDI規格を統一することで、複数の取引先企業ごとに異なる仕様に対応する必要がなくなるため導入コストが大幅に低減できます。また、取引先の増減にもスムーズに対応できるなど業務を効率化するとともにミスの削減も期待できます。
従来のアナログ運用の受発注業務からEDIに移行する際は、自社だけでなく取引先との調整も不可欠になるため、自社の独断で進めることはできませんが、EDIが、受発注企業の双方に業務効率化の恩恵をもたらすことは明らかです。
先述したようにEDIには複数の規格があるため、EDIを導入する場合には業界で標準化されている規格や中小企業共通EDIなど、導入後も容易に拡張できる規格を採用するようにしましょう。
なお、EDIについて、より詳しく知りたい方は下記記事で詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。
受発注システムをデジタル化するまでの8つのステップ
ここでは、受発注システムをデジタル化するためのステップを8つに分けて順に解説していきます。
ステップ① 現状を把握するために業務を洗い出し、フロー図を作成する
電子受発注システムの導入の第一歩は、自社の現行業務を正確に把握することです。受発注業務が属人化し、明確な業務フローが分からないまま業務が行われているケースが少なくありません。例えば、同じ業務なのに担当者ごとに進め方や見積書のフォーマットが異なっているなど、非常に効率が悪い状況です。
そこでまず、現行の業務とフローを可視化し、そうした問題を把握する必要があります。このステップでは、社内の業務に精通している人材をプロジェクトに参加させるとともに、必要に応じて外部のITコンサルタントの招へいも検討すべきです。
業務の洗い出しとフロー図の作成では、通常フローだけでなく例外対応も洗い出すことが重要です。というのも、システム導入後に例外フローが発覚すると、システムでは対応できないが従来のアナログ対応にも戻せないというケースが発生する可能性があるからです。
ステップ② 業務フローを見直し、改善する
業務を洗い出して業務フロー図を作成すると、無駄な業務や非効率な業務の存在に気付きます。例えば同じ目的の帳票が複数の様式で存在しているというケースも珍しくありません。
こうした状態をそっくりそのままシステムに移植しようとすると、膨大かつ複雑なカスタマイズが必要となり、開発コストが大幅に膨らむ上、複雑なシステムが出来上がりその保守・運用コストも大きくなります。そのため、現行の業務フローを細部まで見直し、改善していく必要があります。
ステップ①②までを実施すると、システム導入時の開発工数の削減にもつながるだけでなく、システム化前の段階で一定の業務効率化を図れるようになります。
ステップ③ 導入方法を決定する
先述した、電子受発注システム導入の3つの方法の中から、自社に最適な方法を検討・決定します。
◆対象別に選ぶ電子受発注システム導入の3つの方法
・目的:個人~中小規模のシステムを、費用を抑えて導入したい
⇒方法① BtoB専用のクラウド受発注システムを利用する
・目的:中大規模のシステムで、カスタマイズや外部システムと連携させたい
⇒方法② カスタマイズやシステム連携も可能な「受発注システム」を利用して構築する
・目的:卸売業やEDI連携が活発な業界で使用したい
⇒方法③ EDIを導入する
サービスによって導入費用はピンキリなので、自社のニーズに適した方法を決めることで必要なサービスを絞ることができます。
また方法③の場合は、現時点の取引先間との連携だけでなく将来の拡張性にも目を向け、業界の標準的な規格を採用するように心掛けましょう。
ステップ④ 新システムの導入を社内に宣言する
システム導入が決まったら、全社に向けて電子受発注システムを導入することを宣言し、必要な人材が導入プロジェクトに協力するための体制を整備しましょう。
デジタル化がなかなか進まない原因の一つに利用者の強い反発があります。
多くの人が慣れた方法を捨てて新しい方法を取り入れることには抵抗があり、よほど明確な問題がない限りは現状を変えたいとは思いません。特にデジタル化では、ITへの苦手意識や、熟練の知識やノウハウにおける優位性を手放したくないという気持ちが働きやすいため、非常に強い反発が生まれます。
そのため、経営方針として、業務効率化は企業の存続に関わる課題であるということを、プロジェクト開始前にトップダウンで強く打ち出し、必要な人材をプロジェクトに関与させやすくする土壌を作っておく必要があるのです。
ステップ⑤ 業務を熟知した人材を導入プロジェクトにアサインする
導入プロジェクトのメンバーには必ず業務に詳しい人材を含めましょう。
システム開発が失敗する原因として、「開発会社への丸投げ」があります。システム開発の主体は、システムを導入する側であることを忘れてはいけません。そのため、現場を熟知した人材がプロジェクトに参加し、すべての工程で現場と開発会社との橋渡しを行う必要があるのです。
導入プロジェクトの活動はハードなため、プロジェクトが完了するまではプロジェクトメンバーの本来業務を軽減するとともに、プロジェクトでの働きを評価項目に含めるなどの調整も必要になります。
ステップ⑥ 新システムのテスト計画を策定し、テストを実施する
開発が終了したら、段階的にテストを実施していきます。少人数の担当者に新システムを利用してもらいながら、実際の業務で利用できるかを確認します。
テストで見つかった改善点やバグはすぐに修正し、再度テストを実施します。テスターの範囲を広げてテストを繰り返し、問題がないことが確認できたら、いよいよシステムリリースとなります。
ステップ⑦ 新システムの運用トレーニングを実施する
新システムの本稼動前に操作マニュアルを用意し、現場で新システムを使ってもらえるようにトレーニングを実施します。仕事を理由にトレーニングに参加してくれない人も出てきますので、強制力を持って参加させるような体制を取れるようにしましょう。
また、トレーニング期間はプロジェクトメンバーや開発会社と現場の担当者が交流できる絶好の機会でもあるため、本稼働に向けて信頼関係を築けるよう心掛けましょう。
ステップ⑧ 旧来の業務フローを廃止し、新システムでの運用を徹底する
システムのリリース直後は問題が多発するため、開発者とサポートの体制をあらかじめ整備しておきましょう。
新運用を開始したら、原則として旧来の業務フローでの運用は一切認めない姿勢を示すことが重要です。そのため、例外対応以外で、新システムを利用していない場合のペナルティをあらかじめ明示し、例外対応が必要となった場合の判断方法とフローを策定するなどし、新システムの利用に対する強制力を高めるようにしましょう。
受発注システムのデジタル化の3つの注意点
最後に、受発注システムのデジタル化において特に気を付けてほしいと筆者が思う3つの注意点を紹介します。
注意点① 導入プロジェクトを進める中で、業務フローに変更が生じる可能性がある
例えば、自社あるいは取引先で運用ルールの変更があったり、新規取引で新しい業務フローが追加されたりして、要件定義後のシステム開発の最中に業務フローが変わる場合があります。
そのため、導入プロジェクトでは途中の変更の可能性を考慮した上で、現場を含めた関係者間での全期間を通じて定期報告会を設定し、変更が生じた場合には、今回吸収するか、次のフェーズとするかを適切に判断し、プロジェクト推進に支障が出ないように調整していくことが大切です。
注意点② 現場で業務に自家製ツールを使用している場合がある
現場ではITに強い担当者が独自に開発したツールを使って業務を行っているケースもあります。そのようなツールが業務の鍵となっている場合もあるため、業務の洗い出しでは利用者に協力を仰いで、抽出漏れがないようにしましょう。
注意点③ 新システムの効果を体験の印象と数値で実感してもらう
先述したように、新システムの導入に対しては、現場は少なからず不満や否定的な印象を持たれることが多いため、経営方針としての明示だけでなく、新システムがもたらす成果を実感してもらうことが重要です。
以前筆者が、電子受発注システムの導入プロジェクトを進めていた際も、現場から強い反発を受けていました。しかし、見積書の作成・承認・送付のプロセスが、新システムを利用することで2日間短縮されたことで、現場でも好意的な評価が増えていきました。
新しいシステムが本当に有用なものであれば反発の声は消滅しますから、結果を示して実感してもらえるシステムを構築することが、最も大切です。
まとめ
国内の中小企業における電子受発注システムの2024年時点の導入率は約40%で60%の企業がまだアナログ運用を行っています。今後ますます少子高齢化が進み、人手不足をどのように補っていくのかがより切実な課題となります。また、脱サプライチェーンの動きによって従来の取引環境が大きく変化する可能性もあります。
そうした課題に前向きに取り組んでいくためにはデジタル化が不可欠で、受発注業務においても例外ではありません。
新たにBtoB専用の電子受発注システムの導入を検討されている場合には、インターファクトリーのSaaS型プラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」がおすすめです。最新のセキュリティ、インフラ、充実した基本機能に加え、複雑なカスタマイズや外部システムとの連携も柔軟に対応できるため、企業に最適な電子受発注システムを構築できます。
サービスの詳細や資料のご請求については、下記の公式サイトをご確認の上、お気軽にお問い合わせください。